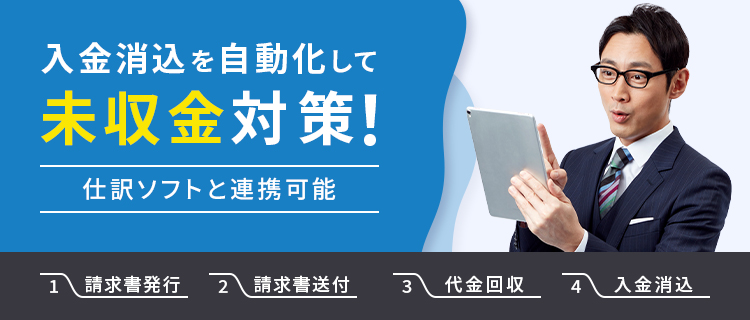請求書(売掛金)の時効はいつ?請求書が有効期限を迎えたらどうなるか解説!

掛売り取引においてやりとりされる請求書は、債権者にとって代金請求の証拠となる大切な書類です。しかし、請求書を送ったからといって、売掛金が必ず支払われるとは限らないことをご存じでしょうか?
実は、請求権には「消滅時効」というものが存在し、支払いがされないまま一定期間が経過すると、売掛金を請求する権利が消滅してしまうのです。
そこで今回は、請求書(売掛金)の時効について、法律に基づきながら分かりやすく解説します。さらに、売掛金が支払われない場合や請求漏れがあった場合の対処法、そしてリスクを回避するためのポイントもご紹介します。
【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説
請求書(売掛金)の時効とは

請求書(売掛金)の時効は原則として5年です。ただし、債権の種類や発生時期により10年の場合もあります。
請求書の時効期間は、以下の表のように区分されます。
▼2020年4月1日以降に発生した債権
| 債権の種類 | 時効期間 | 時効の起算点 |
|---|---|---|
| 一般的な債権(改正民法適用) | ・権利を行使できることを知った時から5年 ・権利を行使できる時から10年 上記のいずれか早い方 |
権利を行使できる時(多くの場合、支払期限の翌日) |
| 商行為によって生じた債権(商事債権) | 5年 | 権利を行使できる時(例:商品の引渡時、仕事の完成時など) |
▼2020年3月31日以前に発生した債権(現在も残存する可能性があるもの)
| 債権の種類 | 時効期間 | 時効の起算点 |
|---|---|---|
| 一般的な債権 | 10年 | 権利を行使できる時 |
| 商事債権 | 5年 | 権利を行使できる時(例:商品の引渡時、手形の支払期日など) |
注: 2020年3月31日以前に発生した短期消滅時効債権(飲食店・小売店の2年、専門家報酬の3年)は、2025年現在では既に時効期間が経過しており、実務上はほとんど関係しません。
時効の起算点
請求書(売掛金)の時効のカウントが始まる起算点は、改正民法では2つの基準があります。
▼改正民法適用債権(2020年4月1日以降)の起算点
| 基準 | 起算点 | 実務上の例 |
|---|---|---|
| 主観的起算点 | 権利を行使できることを知った時から5年 | 債権者が請求できることを認識した時 |
| 客観的起算点 | 権利を行使できる時から10年 | 支払期限の翌日など |
いずれか早く到来する方で時効が完成します。
▼具体的なケース別起算点
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 通常の場合 | 支払期限の翌日 |
| 支払期限が定められていない場合 | 債権者が権利を行使することができる時 |
| 請負代金の支払いが分割払いの場合 | 各分割金の支払期限の翌日 |
| 仕事の目的物の引渡しまたは完成が条件となっている場合 | 仕事の目的物の引渡しまたは完成時 |
時効の援用
消滅時効が成立すると、債権を請求する権利が消滅し、相手方は時効の利益を援用できる(「時効だから支払いません」と主張できる)ようになります。
請求書(売掛金)の時効の利益を援用されると、債権を請求できなくなる可能性があるため、時効期間が経過する前に、時効の完成猶予・更新などの適切な対応をとる必要があります。
請求忘れがあった場合の対処法
自社のミスで請求忘れがあったことに気付いた場合は、速やかに取引先に連絡して謝罪をしたうえで、請求書を再発行して支払いを依頼しましょう。請求忘れは相手に迷惑がかかることはもちろん、自社のキャッシュフローなどにも影響をきたします。請求情報の管理方法を見直すなどして、再発防止に努めましょう。
請求忘れについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
なお、当社の「請求管理ロボ」であれば、1度の登録で請求書発行・送付を自動化でき、明細単位でスケジュール管理が可能なため、請求書の送付漏れや送り先ミス、支払期日の未記載が生じません。
請求書(売掛金)の未払いへの対処法

請求書(売掛金)の未払いがある場合、時効が成立する前に適切な対処をする必要があります。以下のような手順で確認・対応を進めましょう。
・自社の不備などを確認する
・催促メールや電話を入れる
・催促状を送付する
・督促状を送付する
・法的措置を取る
それぞれの流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
なお、当社の「請求管理ロボ」を導入すると、請求書受取側の請求先にも、大きなメリットがあります。
オプションのマイページ機能をご利用いただくと、請求書受取側は発行元に都度問い合わせることなく請求書の管理・照会・ダウンロードが可能となります。
マイページ上で請求書が確認できるため、メールや郵送による請求書が届かないといった問題が防げます。
払い忘れや故意の未払いについても、「自動催促メール機能」で即時通知を徹底できるため、未入金の取引先に迅速なアクションを起こすことができます。
メール送信を決済期限「前後」で設定できるため、事前の入金漏れ防止にも効果的です。
請求書(売掛金)の消滅時効は遅らせられるのか?
以下を押さえることで、時効に関して一定の法的効果を生じることがあります。
なお、督促状の書き方については、以下で詳しく解説しています。
時効の完成猶予
督促状が民法150条に規定される「催告」の要件を満たす場合、時効の完成を6か月間猶予する効果があります。
ただし、これは時効期間をリセットするものではなく、6か月の猶予効果が一度に限って認められるにとどまります。
根本的な解決には、6か月以内に「支払督促」等の裁判上の請求が必要となります。
支払督促については、以下で詳しく解説しています。
内容証明郵便による証拠化
民法150条に規定される「催告」の要件を満たす督促状を送付する際には、その事実を証拠化するために内容証明郵便を用いることが重要です。
これにより、催告を行った日時と内容を客観的に証明できます。
内容証明郵便については、以下で詳しく解説しています。

請求書の消滅時効を防ぐなら「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書の消滅時効を防ぎ、効率的かつ安全な請求書の期限管理を目指される方は、ぜひ株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。
導入企業様からは「請求書発行漏れがなくなった」「イレギュラーな請求書発行の対応がスムーズになり、請求漏れがなくなった」など、好評価をいただいております。
請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに900社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR