インボイス制度の廃止案が挙がる要因とは?廃止の可能性や対策なども紹介
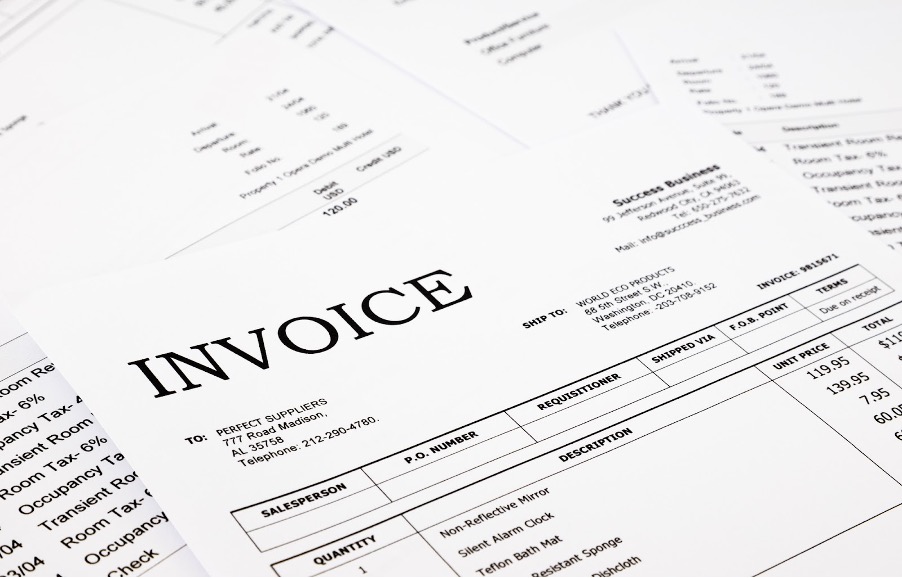
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式が「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に変更され、すでに運用が開始されています。しかし、制度導入後も特に中小企業を中心に経営への悪影響を懸念する声は高まっており、野党から制度の廃止を求める動きも出ています。
この記事では、インボイス制度の何が問題視されているのか、廃止の可能性はあるのか、さらには免税事業者・課税事業者それぞれの立場から見た具体的な対策などについて、詳しく解説していきます。
インボイス制度の廃止・延期案が挙がっている要因
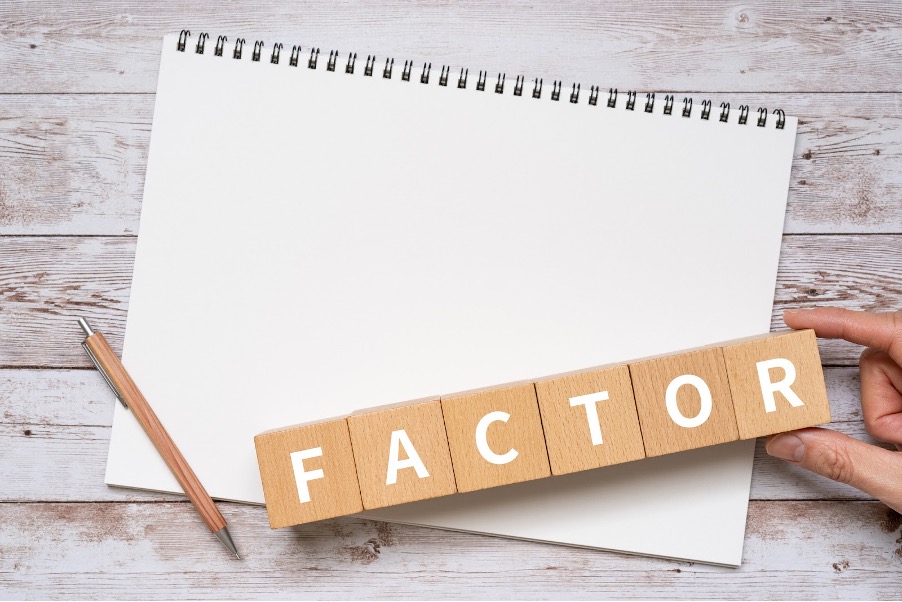
ここでは、インボイス制度の問題点や廃止の声が上がる理由を、免税事業者・課税事業者それぞれの視点から解説していきます。
免税事業者への影響
買い手側の事業者が仕入税額控除を受けるには、インボイスが必要です。しかし、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。そのため売り手が免税事業者のままでは、仕入税額控除が受けられなくなることを理由に、取引先から契約を打ち切られる可能性が出てきます。あるいは打ち切られないにしても、見返りに消費税分の値引きを要求されるかもしれません。
課税事業者になって取引先との関係性の継続を図ることもできますが、そうなると以後は消費税を納めなければならなくなります。これまで丸々利益にできた消費税分が手元に残らなくなることでもたらされる収入減は大きな痛手となるでしょう。特に年間の売上高が1,000万円未満のフリーランスの方や個人事業主の方にとっては、経営の圧迫による廃業や経営破綻にもつながりかねません。
課税事業者への影響
インボイス制度の導入は、課税事業者にも大きな影響を及ぼします。
第1に、経理業務の負担増です。買い手は、売り手から受領した請求書がインボイスの基準を満たしているかを都度確認していかなければなりません。また、納税額の算出もインボイスに記載された消費税額を基に行うことになります。作業が増えることに加え、業務フローの変更が必要になる場合もあるでしょう。
第2に、コストの増加です。既存の会計システムがインボイス制度に未対応であれば、システム改修や新システム導入に伴うコスト負担が避けられません。さらに、先に述べた経理業務の負担を解消するために人員の補充が必要になれば、その分人件費もかさみます。このようなコスト増加は、インボイスを交付する側にもインボイスを受領する側にもどちらにも起こりうる懸念と言えます。
今後インボイス制度はどうなる?どう対応すべき?

このような状況を踏まえると、事業者としては政府の動向を注視しつつ、制度への理解を深め、適切な準備を進めておくことが大切です。万が一、制度の変更や廃止があった場合でも、迅速に対応できるよう備えておくことが求められます。
それでは、免税事業者と課税事業者それぞれの立場から、具体的にどのような対応が必要になるのか見ていきましょう。
インボイス制度は今のところ廃止の予定なし
現時点では、政府はインボイス制度の普及スケジュールを予定通り進める構えを見せており、少なくとも廃止を検討している様子はありません。
しかし、インボイス制度への不満や懸念は導入前から高まっており、2022年6月10日には野党4党共同でインボイス制度の廃止などを盛り込んだ議員立法「時限的消費税減税法案」が提出されました。運用開始後の現在も中小企業を中心に経営への悪影響を問題視する声が根強く、フリーランスや小規模事業者などで作る団体から制度の中止や延期を求める署名も提出されています。今後、こうした声の高まり次第では、政府の方針に変化が生じる可能性も皆無ではないと言えるでしょう。
インボイス制度の問題に対してどう対応すべきか
<免税事業者の対応>
免税事業者の方は、取引先との交渉を早期に始めることをおすすめします。継続的な取引を行っている先には、インボイス発行事業者の登録申請予定の有無を事前に確認し、課税事業者への移行が難しい場合は価格交渉を行うなどの対策を立てておく必要があります。
また、取引先との関係継続のために課税事業者へ移行するか、免税事業者のまま価格交渉などを行うかの判断も求められます。免税事業者がインボイス制度に対応する方法や請求書の書き方は、こちらのの記事で詳しく解説しています。
複数の選択肢を想定したシミュレーションを行い、経営判断の材料を整理しておくことをおすすめします。
<課税事業者の対応>
一方、課税事業者の方は、インボイス制度に対応した会計システムの導入や改修、必要に応じた従業員教育などを計画的に実施していきましょう。取引先に免税事業者が多い場合は、取引価格の見直しについて事前に協議を行い、円滑なインボイス発行ができる体制を整えることも重要です。
インボイス制度の対応は「請求管理ロボ」にお任せ!

インボイス制度へのスムーズな対応をお望みであれば、ぜひ株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。
「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに900社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR








