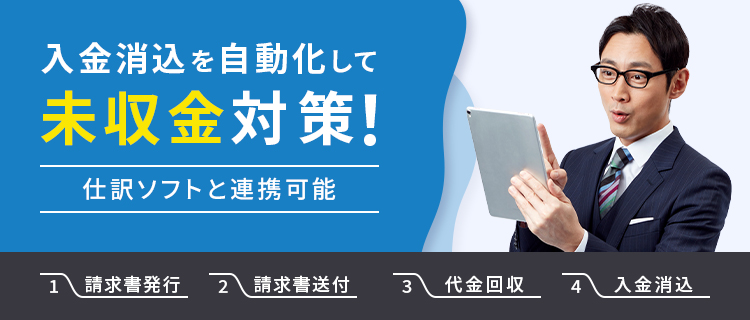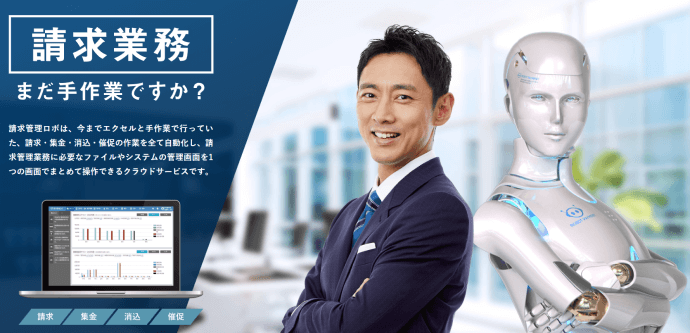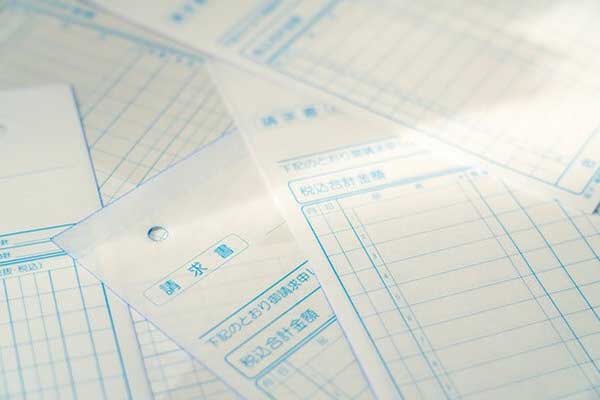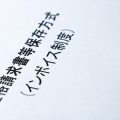請求書に原本は必要?保存方法や紙の請求書原本をPDF化する際の注意点を解説!

請求書はこれまで紙の原本を郵送して送付・受領されることが一般的でしたが、昨今の法改正などの影響によって請求書の電子化が加速しています。
しかし、その一方で、「電子請求書を受け取った場合、請求書原本の保存方法はどうすればいいの?」「紙の請求書を原本として受け取った際、PDFなどに電子化してもいい?」など、新たな疑問も生まれていることと思います。
そこで今回は、上記のポイントについて徹底解説していきます。
【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説
請求書の原本は必要(保存義務がある)
請求書の原本は、法律上でその必要性が定められており、保存義務があります。証憑書類に当たるため、所得税法や消費税法、法人税法などで一定期間保存することが定められており、会社の判断で勝手に破棄することは認められていません。
ただし、近年は電子帳簿保存法の改正により、紙で受領した請求書等についても、スキャナやスマートフォンで読み取り、同法のスキャナ保存要件を満たして電子データとして保存すれば、紙の原本は保管不要(廃棄可)となります。
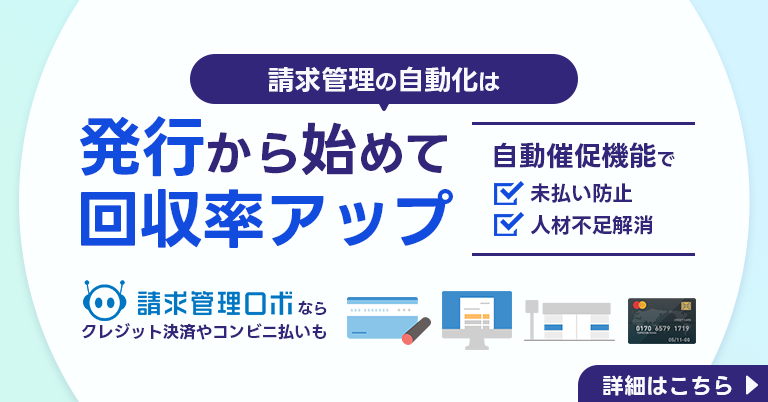
請求書原本の保存方法

では次に、請求書原本を受領した場合の保存方法にも触れておきましょう。
請求書の保存方法は、従来の紙媒体での保存のほか、マイクロフィルムや電子データで保存する方法があります。
紙媒体での保存
ペーパーレス化やIT化が進んだ近年でも、印刷した請求書を郵送してやりとりしている企業は少なくありません。
ただし、紙媒体で請求書を保存するのは、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。
・手動での振り分けによるミスのリスク
・経年劣化による破損や紛失の可能性
・保存するスペースの占有
・検索性が悪く、探しにくい
特に課題なのが、保存するスペースの占有問題でしょう。企業によっては専用倉庫を借りなくてはいけなくなることもあるため、管理の手間やコストがかかってしまいます。
また、2022年の電子帳簿保存法改正に伴い、2024年1月以降、電子取引データは原則として電子データのまま保存が義務付けられ、紙出力での代替は認められません。紙でやりとりした請求書のみが、紙媒体のまま保存可能です。
マイクロフィルムでの保存
マイクロフィルムとは、文書などをカメラで撮影し、10分の1から30分の1程度に縮小撮影する写真技法のことを指します。写真フィルムよりも細かい粒子で構成されるため、請求書だけではなく契約書や図面などの細かい文字や線まで記録できます。
請求書を縮小してフィルムに収めるため、紙媒体で保存するよりも大幅に省スペース化が可能です。長期保存に適しているため、要件を満たせば有効です。
PDF等の電子データでの保存
紙で受領した請求書は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」における重要書類要件を満たせば、PDF等の電子データで保存することが可能です。
紙の請求書をスキャナーなどで読み取るほか、デジカメやスマホで撮影したデータを保存することも認められています。
特に近年は「管理しやすい」「スペースを取らない」と、紙媒体から電子データによる保存に切り替える企業や個人事業主が増えてきています。
ハードディスクやCD、DVD、クラウドサーバなどで管理できるため、とにかく省スペースで検索性が高い点が大きなメリットです。
また電子データで発行した請求書は、電子データのまま保存することが義務付けられています。その際は、真実性や可視性を確保するために電子帳簿保存法の「適用要件」を満たす必要があります。
なお、当社の「請求管理ロボ」の請求書は、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応しており、お客様は何もせず、安心して法令に準拠した請求管理ができるようになります。
また、オプションのマイページ機能をご利用いただくと、請求書受領側は発行元に都度問い合わせることなく請求書の管理・照会・ダウンロードが可能となります。
PDF等に電子化した請求書原本を送付する際の注意点
では、実際にPDF等に電子化した請求書原本を送付するにあたって、どのようなことに気をつける必要があるでしょうか。ここでは、主な注意点を3つご紹介します。
別途原本が必要かを確認する
法改正によりPDF等に電子化した請求書原本の送付は認められていますが、紙の請求書がなくなったわけではありません。紙で受領した請求書の場合には、原本を紙で保存することが認められています。
そのため、取引先から紙の請求書原本の提出を求められるケースもあります。こうした際には、紙の請求書原本の発行に対応する必要があるため、PDF等の電子データとは別に原本が必要かどうかをあらかじめ取引先に確認しましょう。
押印の必要性と形式を確認する
PDF等に電子化した請求書原本で問題となるのが印鑑の取り扱いです。
紙・電子データに関わらず、押印なしの請求書は有効です。請求書は法的な発行義務がある書類ではないので、押印も必須ではありません。ただし取引の証拠書類としては、押印があったほうが有効性が高まるため、相手方の社内ルールによっては押印がないと正式な請求書として受理されないこともあり得ます。
こうしたことから、実務ではPDF化する際に請求書の原本に電子印鑑を押印したり、印影の画像を貼り付けたりする手法が採られることが多くなっています。
押印の有無や形式は取引先によって異なるため、忘れずに確認しましょう。
改ざんしにくいフォーマットを用いる
編集が可能な状態の請求書データは、数量や単価などを容易に修正できてしまい、のちのちトラブルにつながる可能性があります。このため、請求書を電子化する際には、PDFなど改ざんしにくいフォーマットを使用することが一般的です。
しかし、最近ではPDFの改ざんも技術的に可能になってきています。PDFのセキュリティを高めるためには、パスワードを設定して編集を制限したり、電子署名を付与したりする方法があります。これにより、改ざんのリスクをさらに低減できます。
紙の請求書原本を電子データで保存する際の注意点

紙の請求書原本を電子データで保存する際の注意点を3つをご紹介します。
請求書原本の保存期間
請求書原本の保存期間は、法人税法・所得税法・消費税法(インボイス制度)などにより、法人/個人の別、欠損金の有無、消費税の課税事業者かどうか等によって異なります。
目安としては、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(一定の場合は最長10年)、個人事業主は申告区分等により5年または7年となるのが一般的です。インボイス制度の運用上、仕入税額控除等のために適格請求書等や帳簿の保存が必要となる場合があります。
また、会社法上も会計帳簿や事業に関する重要な資料の保存が求められるため、社内規程では10年保存としている企業もあります。自社の状況と最新の取扱いに沿って運用しましょう。
社内規定の整備
電子帳簿保存法の改正により、かつて求められていた「適正事務処理要件(相互けん制・定期検査など)」は廃止されました。
しかし、データの改ざん防止や正確な事務処理を行うためには、引き続き社内での事務処理フローを明確化しておくことが重要です。
具体的には、「いつ・誰がスキャンを行うのか」「スキャン後の紙原本はいつ廃棄するのか」といったルールを定め、社内規程として整備しておくとよいでしょう。
また、スキャナ保存を行うシステムには、タイムスタンプの付与や訂正削除履歴の保存機能などが求められます。
国税庁HPでは改正法に対応した社内規程のサンプルが公開されていますので、参考にすることをおすすめします。自社の事業規模や経営環境などを踏まえて、無理のない運用ルールを策定しましょう。
トラブル対応の方法策定
請求書原本を電子データで保存するために導入したシステムによって、トラブルが発生することもあり得ます。そのため、当該システムとは別にデータのバックアップを取っておくことはもちろん、サーバー障害やセキュリティ障害、あるいは自然災害による停電などが起きた時の復旧に向けた手順を確立しておくことが大切です。
請求書原本の管理効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

デジタル上で請求書原本のやりとりや管理が完結できるシステムをお考えであれば、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。
当社の「請求管理ロボ」の電子帳簿保存法に対応した請求書電子化サービスでは、過去の請求書データをクラウド上でいつでも確認でき、保存管理がしやすくなります。 保存スペースの確保や検索性にも優れています。
請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR